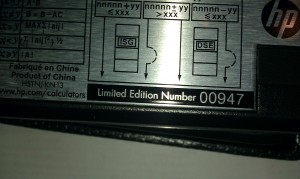hp20bは、発売当初から技術資料で内部の回路およびファームウエアが開示されており、裏面にある接続パッドからのシリアル接続、本格的な開発には、本体裏のケースを少し削ってJTAGコネクタをはんだ付けできるような銅箔パターンなどが用意され、カスタマイズしたければATMELからデベロッパーツールをダウンロードしてどうぞご自由に、という紹介を行っていた。 そこでコアなファンの間ではrepurposing を検討しようという話などもちらほらでていた訳だが、最近まで、自分としてはフォローしていなかった。 2年ほど前の12c+の販売、また今回の15C LEでも、同じシリアルの6ピンパッドが電池室内部にある、ということで、一応リフラシュ可能、で、あらためて見直してみると、ここ数ヶ月で充分実用に耐えうるような WP34Sという科学技術電卓のファームウエアができあがっているようである。
さらにオーバーレイも作成されて、配布しており、hp20/30b を改造できるような環境が整っている。
 30bのほうが、キーボードの出来がはるかによいのだが、中身のエレクトロニクスは同じようだし、自分としては30bがオフィスでのメイン機になっている。 20bはほこりをかぶっていた訳だから そのうちにでてくるであろう、15Cのファームウエアのアップデートの予行練習をかねて20bをフラッシングしてみよう、という気になった。
30bのほうが、キーボードの出来がはるかによいのだが、中身のエレクトロニクスは同じようだし、自分としては30bがオフィスでのメイン機になっている。 20bはほこりをかぶっていた訳だから そのうちにでてくるであろう、15Cのファームウエアのアップデートの予行練習をかねて20bをフラッシングしてみよう、という気になった。
ここで問題になるのはケーブルセットだ。このPDFに詳しいが、自作しようとすると、どうもこの電卓側へのコネクターとピン( 2x3のスプリングピン)のアッシーが簡単に入手できそうにない。幸いなことにHPがケーブルセットを大量に作成させ、これを個人(Gene Wright さん)を通して配布していることがわかったので、送付をお願いした。 頼んでから3日ほどで到着した。
 PCへの接続はRS232である。 中間に消去ボタン(Erase )とリセットボタンの付いたケースがある。 またPC側にはATMELのサイトからSam-BA というフラッシュ用のツールをダウンロードしてくる必要がある。 (書いている時点でのバージョンは2.1)
PCへの接続はRS232である。 中間に消去ボタン(Erase )とリセットボタンの付いたケースがある。 またPC側にはATMELのサイトからSam-BA というフラッシュ用のツールをダウンロードしてくる必要がある。 (書いている時点でのバージョンは2.1)
PCのOSだが、どうもXPが一番トラブルが無いようだ。Windows7に導入してみたが、普通にインストールするとSam-ba_CDCというバージョンしかインストールしてくれない。 (XPだとSam-ba.exe とsamb-ba_cdc.exe の二つの実行ファイルが導入される。 実際にこのケーブルと組み合わせて使うのはSam-ba.exe のほうだ。)
HPのフォーラムも眺めてみたがWindows7 でうまく行った、というコメントがヒットしてこない。
ネットブックにまだXPのインストールが残っているのを思いだし(デュアルブートで普通はUbuntu を走らせている) こちらを使うことにしたのだが、netbook では、さすがにRS232は付いていない。 そこで、USB-シリアルコンバーターをAmazon で注文し(18ドル)これを噛ませて使うことにした。
まずは予行練習の予行練習ということで、HP20bのファームウエアをアップデートしてみることにした。
手持ちのhp20b のファームウエアの日付は2008年6月24日のものだ。
hp.com/calculatorsに行き、”home and home business” ではなく、” business and schools” の売り場のほうからhp20bのページに行くと、”support and drivers” というリンクがある。 このリンクから”Download drivers and software” ->”Cross operating system” とたどっていくと最終的にDevelopment kit をダウンロードするページにたどり着く。 このキットの中に入っているロムイメージ(サイズが128キロバイト、拡張子がbin となっているのでそれとわかる)は2009年10月22日となっている。
最後にフラッシュの手引書をダウンロードし、これを前もって印刷しておく。
この手引書の手順の3、ステップ1から8まで写真で詳しく説明してあるが、ようするに
消去ボタンをおしっ放しにし、その状態でリセットをおしっ放しに、そこで電卓のON/CEをちょい押しし、その後リセットを放し、次に消去ボタンを放す。 最後にリセットをもう一度押し、その後on/CEをおす。 この状態で電卓がONしないことを確認。 この時点で電卓の機能は無くなっている。
これでめでたくファームウエアが消去され、フラッシュの準備が整った、ということになる。 ここでストップすると 20 b はうんともすんとも言わなくなる。 また電池が流れっぱなしになるようなので、ここで一休みするなら、電池をはずしておく必要がある。
ここまでの作業はPC側の準備とはまったく関係なくできるようだ。 フラッシュの作業の中で一番簡単な部分だが、同時にここからリカバリーできなくなる場合が多々あるようで、フォーラムに何件か記事が載っていた。 自分も実は迷路に入りそうになった口で、無事フラッシュが完了したのは次の日である。 ひとつ心強かったのは「死んでしまったようにみえても、フラッシュブートローダーの部分は絶対に動いている。いままでまったくダメにした経験が無い」というhpフォーラムの住民たちのコメントであった。
というわけで、実際のフラッシュの作業は次回に






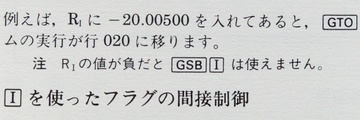 これまた、hp15C LEのイメージロムがオリジナルと同じものだというなによりの証拠か
これまた、hp15C LEのイメージロムがオリジナルと同じものだというなによりの証拠か